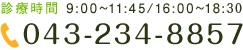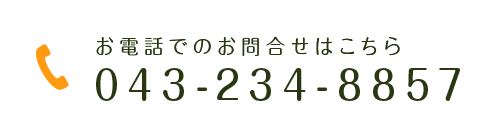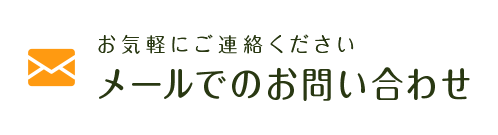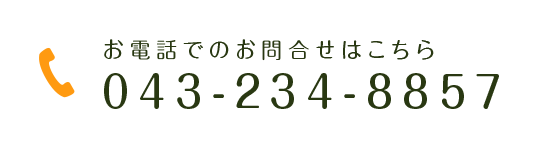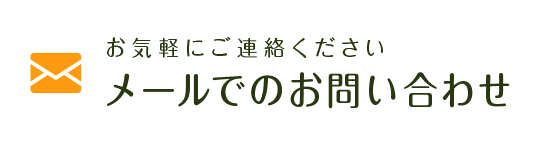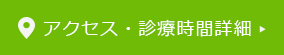前回は、シニアのねこちゃんで多くみられる腎臓病の病状や早期発見について【腎臓病ブログ】掲載しました。
今回は慢性腎臓病の一般的な診断と検査についてお話しようと思います。

 のように、若い時と比べて水を飲む量が増えてきたら要注意です!
のように、若い時と比べて水を飲む量が増えてきたら要注意です!
①血液検査・・・代表的な検査です。血液検査でわかることは現在の腎臓のおおまかなコンディションです。数値が上昇したときは他の検査と組み合わせて原因を探ります。 BUN(血中尿素窒素)や クレアチニン、が代表的な腎臓の状態を知る検査項目です。 さらにSDMA(対称性ジメチルアミン)という検査項目が最近では測定できるようになりました。このSDMAは腎臓機能である糸球体ろ過量の指標となっていまして腎機能検査の新しいスタンダードといわれており、既存の検査より早期に腎臓病を発見できる画期的な検査といわれております。 また治療の管理にも役立つといわれております。
*その他腎臓病の悪化に伴い貧血やミネラルの代謝異常もみられるために、血液ではその他の項目も注目する必要もあります。
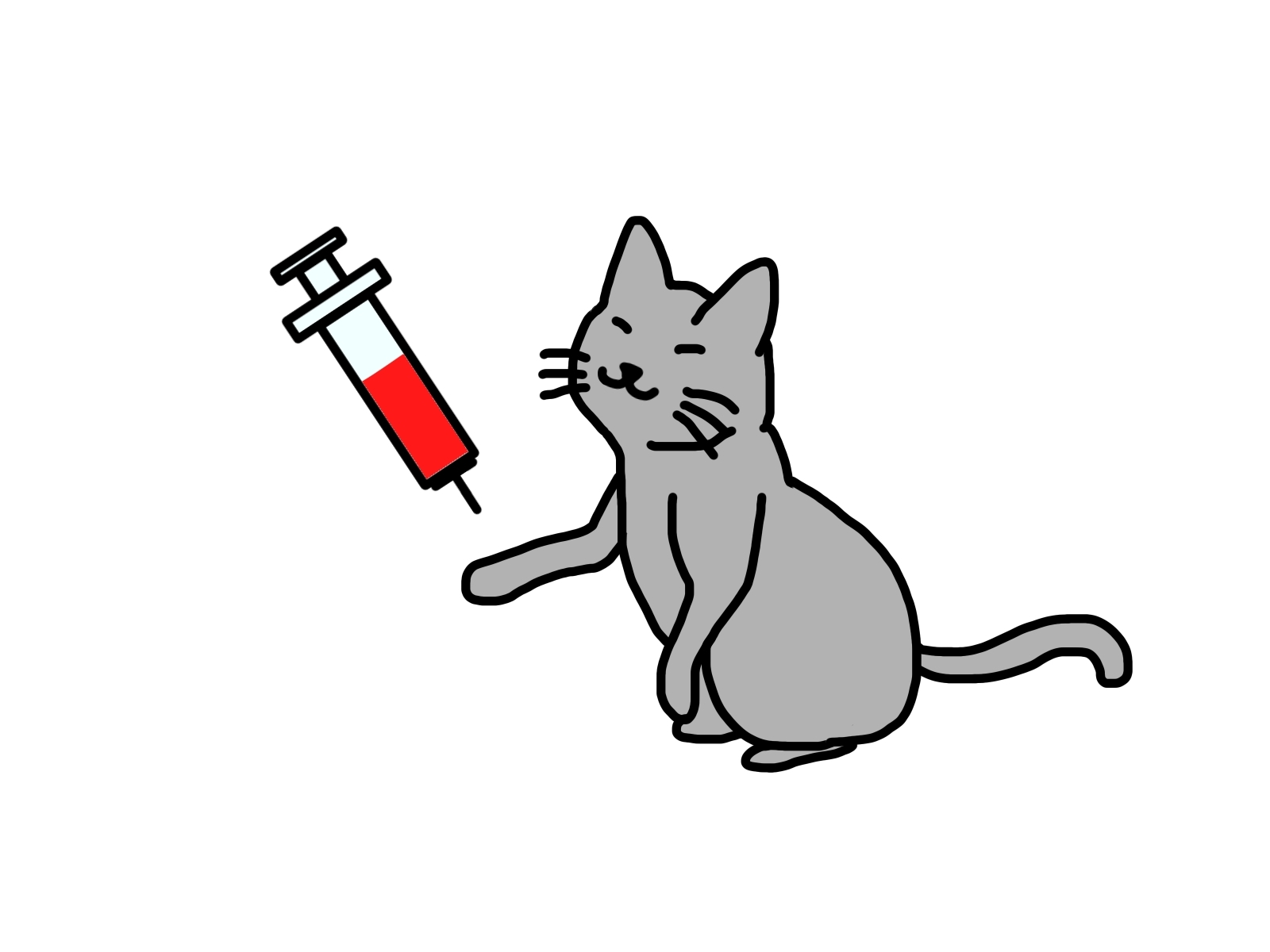
②尿検査・・・古典的な検査ですが、これも重要な検査です。猫の慢性腎臓病の特徴である尿濃縮能力の低下がはじまると尿比重の低下(薄い尿になる)がみられます。 また蛋白尿は腎機能の悪化を加速させるといわれています。尿試験紙で測定するほか尿蛋白クレアチニン比(UPC)で確認します。

③画像診断・・腎臓に何かおきている状況を把握するためにエコー検査や場合によってはレントゲン検査を行います。結石や嚢胞、ウイルス病、腫瘍やリンパ腫などが原因になっている場合もあります。
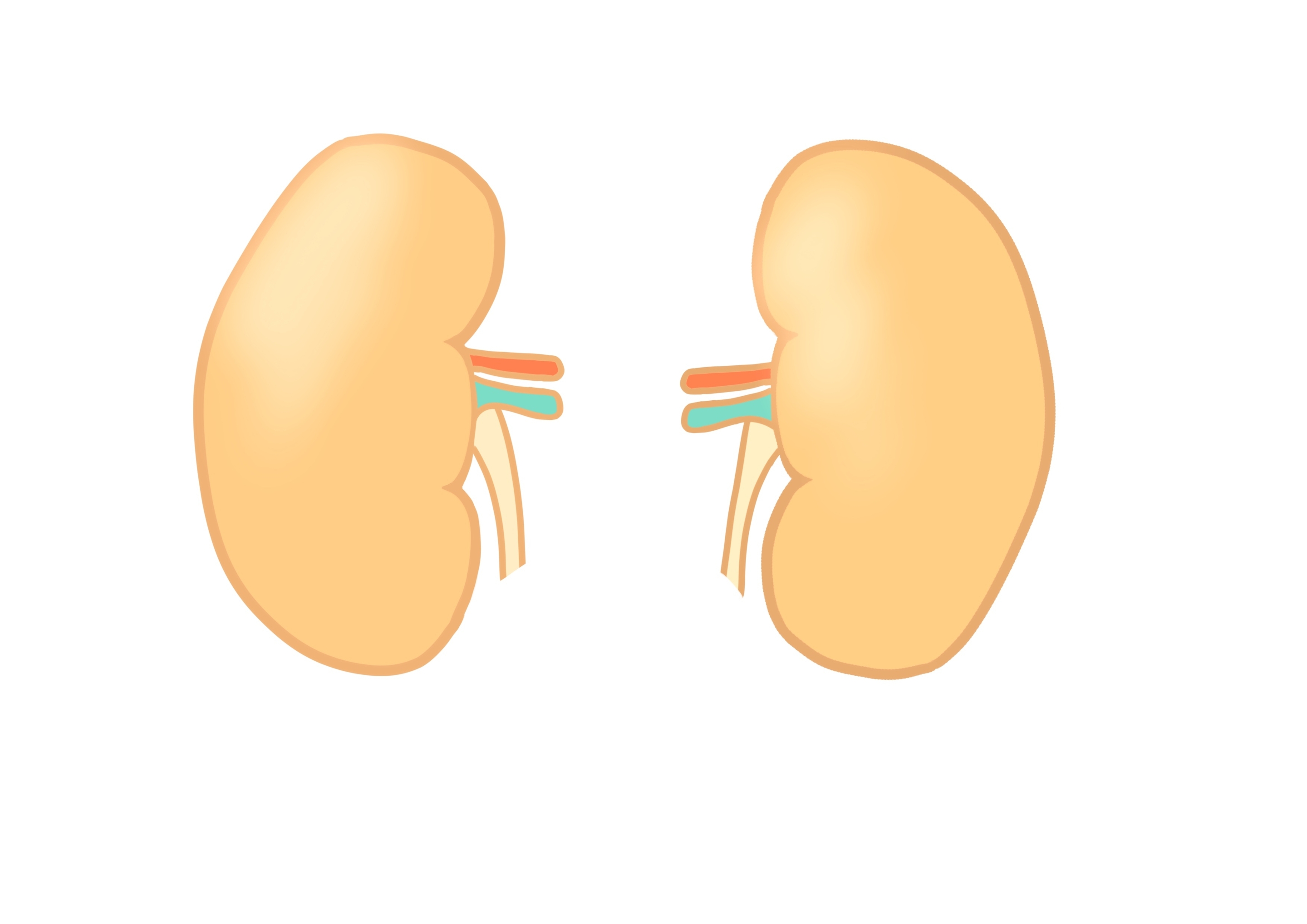
④血圧測定・・慢性腎臓病の合併症として約3割に高血圧があると言われています。高血圧となると蛋白尿がでて腎臓病の進行したり、目の病気になったりします。ただ血圧については、シャイなネコちゃんでは診察中や測定中に興奮状態となってなかなか評価が難しいこともあります。 自宅で測定するのが理想ですが、なかなか難しいです。
自宅で測定するのが理想ですが、なかなか難しいです。

以上、様々な検査を組み合わせて総合的に慢性腎臓病の現在の状況(臨床ステージ)とネコちゃんの症状を組み合わせて、治療していくのが理想です。
もちろん費用や、ねこちゃんの性格等をみて検査、治療を飼い主様と話し合って決めていくのが当院での方針です。